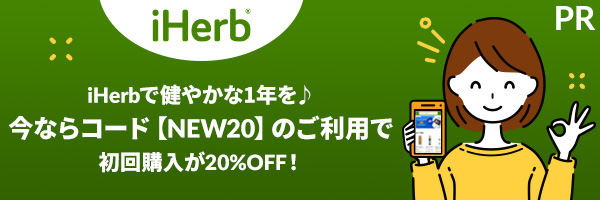落語「葛根湯医者」に登場する「葛根湯」は万能薬!?
落語のまくらに使われることの多い『葛根湯医者』からは、“葛根湯”が江戸時代の人々の生活に、いかに寄り添っていたかがわかります。
江戸時代の人々の日常にあった“葛根湯”
落語のまくらに『葛根湯医者』という噺がよく使われます。
江戸時代のこと。はっつぁん、くまさんといった天然代表のような人々が町医者に行き、「先生、頭が痛いんですが」「おいら、腹が痛いんで」と申し出ると、「ああ、頭痛なら葛根湯を飲みなさい」「腹痛? それなら葛根湯をおあがり」といったように、どんな病気でも“葛根湯”を処方されていたそうです。
しまいには、この町医者、足が痛い人にでも、目の悪い人にでも葛根湯を飲ませるほど。
「はい、次はそちらの方」「いえ、私は付き添いとして来ただけで」「まぁ、いいから葛根湯をおあがり」なぁんて言うものだから、この町医者は“葛根湯医者”と呼ばれるようになって…という噺です。

現代でも認められる葛根湯の幅広い働き
骨折でも目の病でも葛根湯を用いるこの“葛根湯医者”はあまりにもひどいですが、そのぐらい葛根湯が江戸の人々の生活に密着していたのでしょう。
では、現代はというと、「医療用漢方製剤」として厚生労働省が認可している“葛根湯”は、葛根(かっこん)、大棗(たいそう)、麻黄(まおう)、甘草(かんぞう)、桂皮(けいひ)、芍薬(しゃくやく)、生姜(しょうきょう)という7種類の生薬で構成され、「発熱・悪寒・鼻水・のどの痛みなどのかぜの初期症状、鼻炎・中耳炎・結膜炎・角膜炎・扁桃炎・乳腺炎などの炎症、頭痛、神経痛、肩こり」といった症状の時に用いられます。
葛根湯は“かぜのひきはじめ”にだけ飲むものと思っていたら、結構広い効能があるのですね。

やはり葛根湯が本領発揮するのは“かぜのひきはじめ”
効果が幅広いのは、麻黄や芍薬が用いられていることで、頭痛や神経痛、肩こりにも効果が期待できるからだとか。とはいえ、やはり葛根湯が本領発揮するのは“かぜのひきはじめ”。
体がゾクッとしたり、ちょっと喉がいがらっぽかったり、いつもとどこか違う…これはかぜに移行しそうだと、これまでの経験からわかった時、即座に葛根湯をのんでおくと事なきを得たということは、多くの人が経験しているのではないでしょうか。
でも、漢方薬は、その人の体質や状態によって合う、合わないがありますし、薬によっては副作用があるものもあります。合わないと思ったら、すぐに別の漢方薬に替えること。くれぐれも江戸時代の“葛根湯医者”のマネはしないでください。

イラスト/すみもとななみ