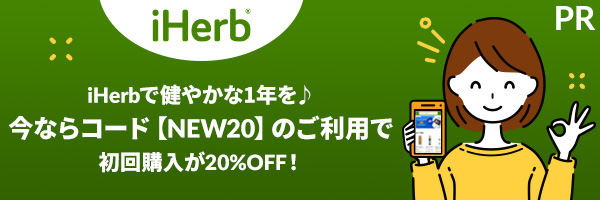私の冷え症が改善できない理由は?|ドクターが教える、本当の冷え対策
まめにやっている冷え症対策が、実はムダだったり逆効果だなんて!? 冷え症のタイプはさまざま。自分の冷えのタイプと原因を知って冷え対策を行えば、今年の冬はぬくぬく冷え知らずに!
目次
「冷え対策」と「冷え症対策」は違う!?
あなたはどんな「冷え対策」をしていますか? 大勢のからだにいいことの読者も、日ごろから冷えやすいという自覚があり、さまざまな冷え解消法を行っているとアンケートに答えています。
からだにいいことの読者が実践する「冷え解消法10」

けれど…しっかり対策しているつもりなのに、あまり効果がないのはなぜでしょう?
「冷えが治らないのは、冷え対策と冷え症対策を混同しているからです」と話すのは、冷え症の研究と治療の専門家、北里大学東洋医学総合研究所の伊藤剛さんです。人間は冷やされると、それに対処するために温かい所に移動したり、靴下や手袋などで保温します。これは行動性体温調節といって、だれもが行う「冷え対策」。でも、これで「冷え症」は治りません。
しかもよく聞く冷え対策法には、科学的根拠がないものもある、との指摘が。
「たとえば、白湯は体によいし、しょうがは胃腸にはよいものです。でも、体を直接温める効果はありません。また、人間には恒常性維持機能があるため、一時的な食べ物の温度によって『冷え症』になることもありません」
医師の伊藤剛さんがみんなの冷え解消法を診断!
そこで多くの読者が実践している冷え解消法について、伊藤剛さんがその効果を判定し、理由を解説してくれました。
寝るときの靴下

「寝るときの冷え対策としては、まず靴下を履きましょう。こむら返りの予防にもなります。それでも冷えて眠れないなら、足指ストレッチがおすすめです。
図のように足指を曲げて、血流をいったん止めると血管を広げる物質が出て、血流が改善されて温まります」
保温は必要

「熱の放出が大きい足裏や手のひらを靴下や手袋でおおう、太い動脈が皮膚近くにあり、熱を奪われやすい首をマフラーでカバーする。これはだれもが必要な冷え対策です。ただし、靴下を重ねるなど、過剰に防寒しても効果は上がりません」
おなかの冷え

「脚が冷えると子宮や卵巣の血管が収縮して血流が悪くなり、下腹部痛を起こすことがあります。それを防ぐには、脚を冷やさないことと、仙骨付近(お尻の割れ目のすぐ上あたり)をカイロで温めることが大事です。おなかを温めると気持ちよいのですが、持続的効果はありません」
生のしょうが

「しょうがを食べてカッと熱く感じるのは、温度受容体を刺激して温感を感じるから。体温を上げるわけではないんです。体を温める成分・ショウガオールは、しょうがを加熱すると生成されますが、ホット紅茶や料理に入れる程度では体を温めるほど増えません」
そもそも冷え症って? 冷え性との違いは? その対策は?
西洋医学では、原因がわかっていて起こる「冷え」、例えば甲状腺機能低下症や閉塞性動脈硬化症などは治療の対象ですが、それ以外の原因がわからないものは、単に冷えに敏感な性質、つまり「冷え“性”」とされ、治療の対象にはなりません。
一方で東洋医学では、症状の訴えがあれば「冷え“症”」として治療の対象とします。伊藤さんが冷えを訴える多くの患者を東西医学の両面から研究・治療してきた結果、冷え方には大きく4タイプあることが判明しました。
「自分の冷え症タイプを知り、その原因に合った抜本的な改善法を行うことが大切です」
4つの「冷え症タイプ」あなたはどれ? 対策は?
いちばん多い「下半身型」

【なぜ起こる?】
その原因は腰やお尻に! 仙骨と股関節をつなぐ梨状筋が、運動不足などが原因で硬くなり、坐骨神経を圧迫。交感神経が緊張して、脚の血管を締めてしまうため、動脈の血流が減って下半身が冷えます。
【改善するには】

梨状筋(りじょうきん)ストレッチで、お尻中央が痛いかどうかをチェック。痛ければ梨状筋が硬くなっているので、このストレッチで緩めます。また、ウォーキングなどで下半身を動かすのも有効。漢方薬や鍼灸治療も効果的です。

特におすすめは、ソフトボールを使ったツボのマッサージ。臀中(でんちゅう)のツボはお尻の真ん中あたり、梨状筋に重なる大殿筋にあり、ここをほぐすと深部の梨状筋もほぐれて下半身の血流が上がります。
●マッサージのやり方
床やベッドの上に寝てソフトボールを臀中の下に挟み、体を斜め45度に傾けて体重をかけて押します。1回30秒まで、1日1〜2回まで。押し過ぎには注意!
若い女性に多い「四肢末端型」

【なぜ起こる?】
食事量や筋肉量が不足していると、熱が十分に作れません。すると、体温低下を防ぐため、交感神経が過剰に働き、末しょうの血管が収縮。その結果、手先や足先の血流が減り、冷えます。
【改善するには】
体の熱量不足が原因なので、まず、食事量を増やすこと。そして、食べたときの産熱量が多いたんぱく質を積極的に摂ること。
それと同時に、運動量を増やすこと。ラジオ体操のように、全身の筋肉を大きくバランスよく動かす運動を習慣化して、熱を作るのも大切です。
足先の冷えから腰痛や頭痛を誘発しやすいので、足指ストレッチ(先に解説した、寝る時の靴下の項を参照)で足先を温めるのも効果的です。
一見冷え症に見えない「内臓型」

【なぜ起こる?】
生まれつき副交感神経の働きが強い人に多い。交感神経の働きが弱いため、寒い環境でも末しょうの血管が収縮せず、熱をどんどん放出。内臓の温度が低下してしまいます。
【改善するには】
熱が逃げ過ぎて体の内部が冷えるので、まず重要なのが保温です。ただし、汗をかきやすいので、温め過ぎも禁物。熱がこもらないよう、通気性のよい素材を選びましょう。
と同時に、交感神経の働きを強化したほうがよいので、ウォーキングやランニングなど、全身を使う運動で交感神経を刺激することも必要です。このタイプには、漢方薬も有効です。
寒気を感じる「全身型」

【なぜ起こる?】
基礎代謝が低く、体内で十分な熱が作れないため全身が冷えます。ストレスや不摂生な生活が要因となるケースが多い。なかには甲状腺の機能低下が原因となっている場合もあります。
【改善するには】
体の内側も外側も冷えているので、熱が逃げないように保温することが重要です。そして、熱を生み出すために、食事やたんぱく質の量を増やすことを心がけて。
また、代謝の悪さをカバーし、心肺機能を高めるために、運動を習慣化しましょう。ラジオ体操のように、体を大きく動かす運動をゆっくり行うのがおすすめです。漢方薬での治療も効果的です。
さらに上記4タイプのほかに、かかと、背中、二の腕など、ある一部だけに冷えを感じる局所型や、各タイプが合併した混合型もあります。
全てのタイプに共通する原因が運動不足やストレスなので、運動習慣とメンタルケアには特に気をつけましょう。
イラスト/石村とも子 みやこしさとこ
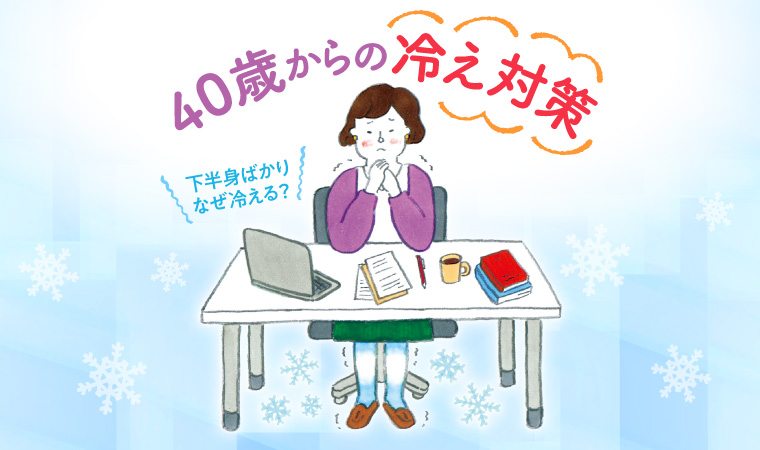
冷え症さんにはツラ~い季節。特に下半身の冷えにお悩みの方も多いのでは。冷えの原因を知って正しく対処すれば、じつは改善できるんです。
[ 監修者 ]