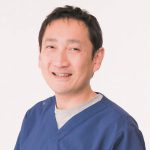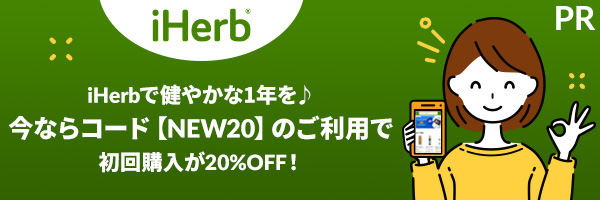ストレスによる食べすぎも防げる!「整顎(せいがく)カムトレダイエット」
コロナ太りを解消したい人にぴったり!食べ過ぎを自然に防ぐ方法が「整顎(せいがく)カムトレダイエット」です。コツはよく噛むことと顎をゆるめること。今すぐ始めましょう。
「VASスケール」を使って満腹感を客観視
よく噛んで食べ過ぎを自然に防ぐダイエット法が「整顎(せいがく)カムトレダイエット」です。
この方法は「VAS」という指標を用いるのが特徴です。
「VAS」というのは、カイロプラクターや医療関係者が用いる「ビジュアル・アナログ・スケール」のこと。
もともとは痛みを1~10の数字で報告し、数値が減れば治療効果があったと評価する指標ですが、それを「満腹感」「空腹感」の指標にするのがポイントです。
空腹は「0」、満腹を「10」とした場合、今のお腹の具合は?と自分に聞いてみます。

お腹が空いて、今すぐ甘いものが欲しいと思ったけど、自分に聞いてみたら実は「5」ぐらいだったから、もう少し待とうかなとか。ランチにお弁当を買ってきたけど、食べる前が「2」だったから全部食べたら「12」ぐらいになりそう。少し残そうかな、など。
「腹八分目」と言われてもなかなかできなかったのが、食べる前後の空腹度合いを数字にするだけで、ひと口残すことができたり、間食が減ったりと、行動が変わります。
数字を思い浮かべることで、本能だけでなく理性も働くので食欲がセーブできるのではとのこと。
イライラなどの感情を和らげるために空腹でないのに食べてしまうことをエモーショナル・イーティング(感情摂食)と言いますが、これもこれも阻止できそうですね。
よく噛むことで「VAS」の数値が低くても満腹感が得られる
そして食べるときのポイントは「よく噛むこと」。
顎と咀嚼筋をしっかり働かせて、食べ物を細かく噛み砕き、整理整頓しながら胃にすき間なく食べ物を埋めていくイメージで食べると、「10」に届かない量の食事でも「8」ぐらいで満腹感を得られるようになります。
顎をよく動かすことで、「よく食べた」という実感が得られることも、食べ過ぎを防ぐことにつながります。
食べる前に顎をゆるめてリラックスすることもドカ食い防止に
さらに食べる前には顎をゆるめると、副交感神経が優位になってゆったりした気持ちで食事に集中でき、本能のままに食べるというような食べ方がなくなるのだとか。
顎をゆるめるエクササイズもぜひ実践してみてください。
【ゆる顎エクサ】
上を向いて「ポカン」とし、そのまま30秒ぐらいキープします。
口は必ずしも開けていなくても、口の中で上下の歯の間を開けるだけでも大丈夫です。
口を開けた場合は、呼吸は鼻から行うようにしましょう。

「ポカン」としたまま、左右にゆっくり倒したり(5往復)、左右にゆっくり回したり(5往復)すると、さらに顎をゆるめることができます。


このダイエットはずっと続けるのではなく、1カ月など限定で行うのがおすすめだそう。
自宅にいる時間が増えて、つい食べすぎてしまうという方は、まずは3日間でも実践してみてください。
カムトレオンラインサロンのお知らせ
「よく噛むこと」を毎日楽しく実践して、健康に美しくなる!をコンセプトに、「噛むことのからだにいいこと」を学び、みんなで実践するコミュニティ(無料)がFacebookの「カムトレオンラインサロン」です。今回ご紹介したVASオリジナルスケールのプレゼントも行っていますので、ぜひのぞいてみてください。
カムトレオンラインサロン

カムトレオンラインサロンのメンバー64人。健康雑誌『からだにいいこと』から生まれた、 「噛むことのからだにいいこと」を学び、 みんなで実践するコミュニティ(無料)です。…
[ 監修者 ]